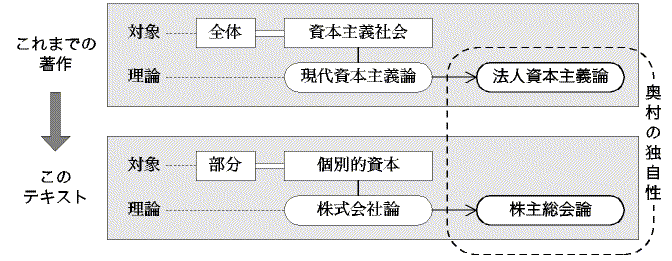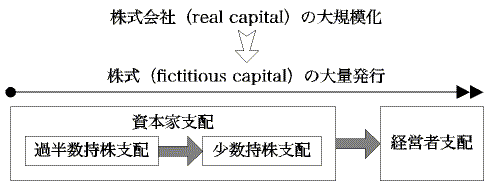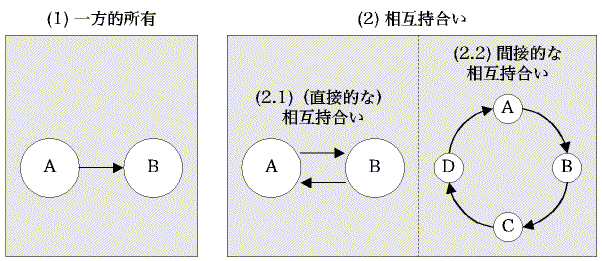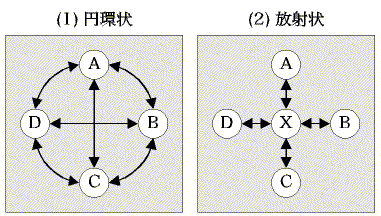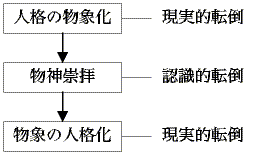課題と構成
周知のように,奥村はこれまで法人資本主義論で名前を売ってきた。それでは,このテキストの主観的な位置付けはどのようなものであろうか。
先ず最初に,奥村の問題関心は資本主義一般にはなく,ただ日本資本主義にのみあるということが確認されなければならない。とは言っても,これについては,問題点のところで扱う。われわれは何よりもまず,彼の主観に即して彼の主張を理解し,これによって彼の見解を批判しなければならない。以下では,これを前提にして,奥村自身による本書の主観的な位置付けを確認する。
第一に明らかであるのは,奥村の主観的意図においては,奥村が著作の順序として全体から部分に移行しようとしているということである (注1) 。これまでの著作では,奥村はこの社会の全体──資本の社会的なシステム,または資本主義社会──の考察を試みてきた。このテキストでは,彼は,資本主義社会の構成部分──個別的資本──の考察を試みている。
第二に確認しなければならないのは,彼が,マルクス経済学者たち,近代経済学者たち,社会学者たち,経営学者たちと全く同様に,事実上,資本主義社会の理論を“現代資本主義論”として展開してきたということである。だからこそ,首尾一貫するためには,彼は個別的資本の理論をもまた,“現代的”な個別的資本の理論──他の多くの論者たちと同様に株式会社論──として展開しなければならないということである。
それでは,第三に,彼の独自性はどこにあるのか。このことは彼が日本資本主義の特殊性の解明にしか興味をもっていないということによって,一意的に決定されるのではないが,しかし制約されている。先ず,全体については,彼は現代資本主義論を法人資本主義論として展開してきた。次に,部分については,彼は株式会社論を株主総会論として展開しようとしている (注2) 。これが彼の独自性である(以上,図1)。
内容要約
第1章 株主総会がなぜ問題になるのか
第1章では,奥村は,株主総会の理解の必要性を訴えるために,三つのトピックス──第一に総会屋スキャンダル,第二に株式会社のホンネとタテマエとの乖離,第三に株式会社における経営者に対するチェック機能の問題──を取り上げている。しかし,奥村にとって,恐らく,総会屋スキャンダルは社会意識に対していまここで呈示されているトピックスであるのに過ぎないのであろうから,理論的にはホンネとタテマエとの分離,およびチェック機能の問題こそが二つの柱をなすのであろう。
株式会社におけるホンネとタテマエとの乖離の問題は正当性に即した議論であり,これに対して株式会社におけるチェック機能の問題は機能性に即した議論である。あるいは,両者とも社会性に即した議論であるが,前者は私的な社会性に即した議論であり,これに対して後者は社会的な社会性に即した議論である。あるいはまた,両者とも正当性に即した議論であるが,前者は単純な商品流通から発生するような,本来的な正当性に即した議論であり,これに対して後者は資本主義的な商品生産から発生する機能性をだらしなく承認するのに過ぎないような,破綻した正当性に即した議論である。現代的な社会的システムは,前者では唯一無二の絶対的なシステム,真善美であり,これに対して後者では他のシステム(封建制および社会主義)と比較してヨリマシな相対的なシステム,必要悪である。
1. 総会屋スキャンダル
総会屋スキャンダルの問題提起:商法改正(単位株制度と利益供与の禁止規定)にも拘わらず,総会屋スキャンダルが後を絶たない。総会屋は日本(及び韓国)にしかない特殊な職業である。常識で考えると,(i)もし総会屋が暴力を振るうのであれば,経営者は刑事事件として警察に総会屋を取り締まってもらえばいいし,(ii)もし総会屋が嫌がらせの質問をするのであれば,経営者は総会でそれに答えればいい。従って,総会屋スキャンダルを理解するためには,(a)総会屋事件の個別的な事実の集積ではなく,株主総会の一般性を明らかにしなければならない;しかしまた,(b)総会屋は日本にしかない以上,株主総会の一般性とは言っても,株主総会一般の一般性ではなく,特殊的な日本型株主総会の一般性を,すなわち日本の株主総会の特殊性を明らかにしなければならない (注3) 。
2. ホンネとタテマエとの分離
2.1 会社民主主義・株主主権
会社民主主義・株主主権というタテマエ:株式会社では,最高機関である株主総会での表決によって取締役が選出され,従って主権があるのは株主であるということになっている。この点で,会社民主主義は政治的民主主義に類似している。とは言っても,一人一票ではなく,一株一票であるから,それは「金持ちのための民主主義」(第15頁)なのであるが。
(1)会社民主主義の破綻:ところが実際には,株主総会は経営者支配を正当化するための単なるセレモニーでしかない。だから,会社民主主義は単なるタテマエ──それどころかフィクション──に成り下がっている。
(2)株主主権の破綻:株主主権は個人株主を前提している。ところが実際には,日本では,発行済み株式の六割以上が法人の所有に帰しているから,株主とは会社のことである。それ故に,“株式会社は株主のものである”というタテマエは,実際には,“株式会社は株式会社のものである”という同義反復であるのに過ぎなくなってしまっている。
2.2 一株一票,株主平等の原則
一株一票,株主平等の原則というタテマエ:株主総会での表決では一株一票の原則に基づいて行われる。この点は株主に応じて代わりはしないから,この原則は株主平等の原則でもある。ところが実際には,以下に見るように,この原則は単なるタテマエになり果てている。
(1)無議決権株:優先株など。
(2)多議決権株:ゴールデンシェアなど。
(3)単位株制度:一株一票,株主平等の原則に反する実態の中で,日本に特有であるのは単位株制度である。と言うのも,日本では,表決はおろか,そもそも「一株どころか,九九九株〔──額面50円の場合──〕の株主も株主総会に出席できない」(第22頁)からである。
自己株式取得:自己株式には議決権が与えられてはならない(商法241条2項)。これは一株一票,株主平等の原則というタテマエに反するが,上記の3つの場合とは異なって,資本充実の原則という別のタテマエによって要請されている (注4) 。ところが,日本では,株式相互持合いによって事実上の自己株式取得が──しかも例外的ではなく普遍的に──妥当している。これもまた,タテマエに反するホンネの部分である。
2.3 資本多数決の原則
資本多数決というタテマエ:株主総会での議案は多数決で表決されなければならないが,それには当然のことに,定足数の充足が大前提である。取締役の選任のためには,出席している株主が所有する株式数は発行済み総株式数の三分の一以上でなければならない。
委任状・書面投票:ところが実際には,定足数は,専ら委任状・書面投票によって──しかも法人株主の委任状・書面投票によって──充足されている。
2.4 株式会社の最高機関
株式会社の最高機関というタテマエ:株主総会は株式会社の最高機関である。
総会権限の縮小:ところが実際には,委任状による株主総会運営の普及に伴って,株主総会の権限も絶えず縮小されてきている。
3. チェック機能
機関としての株主総会:コーポレートガバナンスの問題として現れているのは会社支配の問題であり,経営者に対するチェック機能の問題である。経営者に対するチェック機能を果たすということが期待されている機関としては,何よりもまず株主総会がある。しかし,既に見たように,株主総会はチェック機能を果たしていない。また,経営者に対するチェック機能を果たすということが期待されている機関としては,それ以外に取締役・監査役がある。もし株主総会がチェック機能を果たさなければ,これらの機関もまたチェック機能を果たしえないということについては,第2章で考察される。
個々の株主:機関としての株主総会とは別に,個々の株主も株主代表訴訟によって経営者をチェックし得るはずである。93年の商法改正による訴訟手数料引き下げに伴って,株主代表訴訟も増えてきた。しかし,株主代表訴訟は,実質的に取締役が支配している会社の利益のために,観念的に会社を支配するべき株主が取締役を訴える訴訟である。従って,会社のために取締役が行う一切の不正行為を,株主代表訴訟は訴え得ない (注5) 。
第2章 株主総会はなぜ形骸化したのか
第2章では,奥村は株主総会形骸化=経営者支配の原因を明らかにしようとしている。その際に,奥村はバーリ・ミーンズ以来の伝統に立って,結局のところ,株券に──擬制資本に──それを求めようとしている。
奥村にとっては,日本資本主義とアメリカ資本主義との区別性こそが──従ってまた,資本主義の一般性ではなく,日本資本主義の特殊性こそが──決定的に重要であるから,日本とアメリカとの類型論として,株式の分散・集中を考察している。すなわち,本書の構成では,(1)アメリカでは株式が分散し,(2)日本では株式が集中しているということに力点が置かれている。われわれは寧ろ,全く同じ事実を以て,資本主義の発展として把握する。奥村が空間的に展開しているものを,われわれは時間的に展開するわけである。
経営者支配の二つの類型:アメリカでも日本でも経営者支配が行われている。しかし,その原因は両国の間では全く異なる。経営者支配現象が妥当しているのは,アメリカでは個人投資家に株式が分散しているからであるのに対して,日本では法人に株式が集中しているからである。
1. 株式分散──アメリカの場合
1.1 個人投資家への株式分散
個人投資家への株式分散:バーリ及びミーンズ,ラーナーらが実証的に解明しているように,経営者支配は株式会社の必然的な産物である (注6) 。経営者支配の根拠は個人投資家への株式分散であり,その条件は委任状制度である。
(1)過半数持株の資本家支配:そもそも最初は過半数の株式を所有する資本家が会社を支配していた。しかし,real capitalとしての株式会社の規模が大きくなると,fictitious capitalとしての株式の発行数も増大する。従ってまた,傾向的には,株主の人数も増大する。
(2)少数持株の資本家支配:この過程の中で,資本家が会社を支配するためにはもはや過半数の株式の所有は条件ではなくなる。こうして,絶対的には少数の──但し相対的には多数の──株式しか所有していない資本家が会社を支配するようになる。
(3)経営者支配:しかし,この過程がさらに進むと,やがては会社支配はもはや株式の所有には基づかなくなる。こうして,資本家に取って代わって,経営者が会社を支配するようになる。これが経営者支配である。ここで初めて経営者支配が生まれるのである(以上,図2)。
委任状制度:「委任状制度は株主から権利を奪って,経営者が会社を支配する手段として利用された」(第55頁)。「もしこの制度がなければ経営者支配は進まなかったかもしれない」(第55頁)。
1.2 機関投資家への株式集中
機関化現象:しかし,第二次大戦後には,個人投資家への株式分散とは逆に,機関投資家──年金基金,投資信託,生命保険──への株式集中が進展した。
機関化現象と法人化現象:機関投資家と法人株主とは全く異なる。〔第一に,〕機関投資家が受益者である個人の代理人として株式を保有であるのに過ぎないのにたいして,法人株主は自己の資産として自己自身で株式を保有しているからである (注7) 。
株主総会での機関投資家のビヘイビア:(a)サイレントパートナー;これまで機関投資家はサイレントパートナーであった。そもそも機関投資家が株式を保有しているのは,受益者に還元するためにである。もし機関投資家が経営者に不満を抱くならば,株式を売却するであろう。これはウォールストリートルールと呼ばれる。(b)発言する投資家;しかし,最近では,機関投資家が株主総会で発言するようになってきている (注8) 。
2. 法人への株式集中──日本の場合
2.1 法人への株式集中
法人への株式集中:日本でもアメリカと同様に経営者支配が確立している。しかし,経営者支配が確立したのは,アメリカでは個人に株式が分散したからであったのに対して,日本では法人──特に大企業──に株式が集中したからである。
法人の株式所有の諸類型:法人の株式所有には,一方的所有と相互持合いという二つの類型がある。二つの法人を考察すると,もし一方の法人が他方の法人の株式を所有しているが,他方の法人は一方の法人の株式を所有していないのであれば,この二法人の間には,一方の法人が他方の法人の株式を一方的に所有しているという一方的所有が成立している。これに対して,もし一方の法人が他方の法人の株式を所有しており,それと同時に,逆に他方の法人も一方の法人の株式を所有しているのであれば,この二法人の間には,相互持合いが成立している。しかしまた,多数の法人を考慮に入れると,もし一方的所有の連鎖が出発点に戻ってくるのであれば,たとえこの連鎖を構成するおのおのの二法人の間では一方的所有しか成立していなくても,この連鎖の全体については相互持合いが成立している。二法人の間での相互持合いが直接的な相互持合いであるのに対して,これは間接的な相互持合いである。従って,相互持合いはまた直接的な相互持合いと間接的な相互持合いという二つの類型に分かれる(図3)。
多数の企業の間での持合い:多数の法人を考えてみると,多数の法人の間での相互持合いには(1)円環状の持合いと(2)放射状の持合いという二つの類型がある。円環状の持合いとは,グループ内の各企業の間で相互持合いが成立しているような類型のことである。放射状の持合いとは,一つの中心企業と多数の周辺企業との間では相互持合いが成立しているが,しかし多数の周辺企業の間では相互持合いが成立してはいないような類型のことである (注9) (図4)。
2.2 株式相互持合いの諸問題
株式持合いの特殊性:株式持合いは個人間でも機関投資家間でも成立し得ず,法人間でしか成立し得ない。
事実上の自己株式取得:法人の株式相互持合いは事実上,自己株式取得である。従って,それは自己資本充実の原則に反している。
経営者間での相互信認:相互に株式を持ち合っている二法人の間では,もし一方の法人の経営者が他方の法人の株主総会で他方の法人の経営者の選出に反対するならば,他方の法人の経営者も一方の法人の株主総会で一方の法人の経営者の選出に反対するであろう。それならば,両者の経営者はそれぞれの株主総会でいずれも落選してしまうであろう。それ故に,両者の経営者は両者の株主総会で相互信認──具体的には委任状・議決権行使書面の交換──を行い合う。
相互信認の一般化:このように,そもそも相互信認は機関投資家の株式所有からも法人の一方的所有からも区別される法人の株式相互持合いの独自性から発生した。しかし,ひとたび相互信認のシステムが法人資本主義のシステムの不可欠な構成要素として確立するやいなや,今度は相互信認は機関投資家の株式所有の場合にも法人の一方的所有の場合にも貫徹するようになる (注10) 。
3. 経営者と株主総会
私的所有者以外のチェック機関:既に見たように,個々の株主も機関としての株主総会も経営者をチェックし得なかった。それでは,社内取締役,監査役および社外取締役は経営者をチェックし得るのであろうか。
支配の類型:誰が会社の支配者であるのかということは,誰が経営者を決めているのかということによって決まる (注11) 。その類型においては,従業員と経営者とは根本的に異なる以上,たとえ経営者が従業員出身であっても,その支配が従業員支配になるとは限らない。何故ならば,従業員が経営者を決めているとは限らないからである (注12) 。
(1)社内取締役によるチェック:株式会社のタテマエでは,取締役が社長を選ぶ (注13) 。それ故に,取締役が経営者をチェックし得るはずである。しかしまた,株式会社の実際では,株主総会で取締役として選出される取締役候補を選出するのは社長である。それ故に,最初には取締役が社長を選び,その後で社長が取締役を選ぶ。そもそも社長が経営者支配を行っている以上,取締役(会)が有効にチェック機能を果たすためには,取締役(会)の社長選任──社長の取締役選任ではなく──の第一次性が不可欠である。ところがまた,取締役が社長を選び,社長が取締役を選ぶというこのサイクルの中では,必然的に転回が生じる。経営者支配現象を根拠にして,またサイクルの悪無限性を条件にして,やがては,最初には社長が取締役を選び,その後で取締役が社長を選ぶようにになる。取締役(会)の社長選任の第一次性は社長の取締役選任の第一次性に必然的に転回する。ところがまた,正に経営者支配現象が前提される以上,社長の取締役選任は社長の自己措定(自分の子分を産むということ)であるのにほかならない。それ故に,結局のところ,「これは社長が自分で自分を選んでいるのと同じである」(第84頁)ということになる (注14) (以上,図5)。
- 図5 選任法則の転回
-
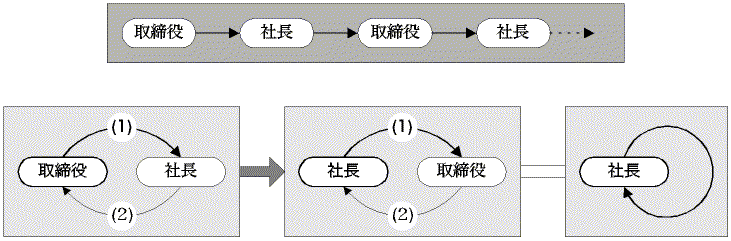 [説明]
[説明]
だからまた,そもそも社内取締役によるチェックは自立的には機能し得ないのである。
(2)監査役・社外取締役によるチェック:このように社内で社長と取締役との馴れ合いが発生している場合に,チェック機能を果たすということを期待されているのが社内外の監査役,および社外取締役である。確かに,アメリカでは,社外取締役が経営者をチェックするということもある。しかし,日本では,株主総会が機能していない以上,結局のところ,監査役・社外取締役を決めるのも社長であるから,彼らにチェック機能を期待するということはできない。
小括:こうして,結局のところ,もし経営者の行動をチェックするべきである諸機関──社内外の取締役・監査役──を選出する株主総会が活性化するようになり,社長のゴマすり相手以外の者をそれらの諸機関として選出するようにならなければ,経営者に対するチェックは不可能である。それ故にまた,問題は株主総会に収斂する。
問題点
I.全般的問題
1.フレームワークについての確認
日本資本主義批判をベースにして資本主義批判をするのか,それとも資本主義批判をベースにして日本資本主義批判をするのか。一言で言って,日本資本主義批判をするのか,それとも資本主義批判をするのか。
2.株式会社についての確認
諸物象の人格化の現実化形態は空間的(国ごと)・時間的(時代ごと)に様々に相異なる。このことは,ヨリ特殊的に株式会社という法制度的な(juristisch)形態,すなわち法制度的な形態としての株式会社についても,ヨリ一般的に社会的なシステムという制度(institution),すなわち制度という姿態で現れる限りでの社会的なシステムについても,妥当する。それ故にまた,問題は資本の一般的理論における株式会社の意義である。
以下では,われわれは,いくつかの理論的な問題を踏絵にして,株式会社認識の躓きの石を明らかにする。
A.私的労働の止揚か,それとも私的所有の止揚か
現代社会は,単純な商品流通としてわれわれの眼前に現れてくる。単純な商品流通の諸表象──自由・平等・私的所有──こそが現代社会の自覚的原則であり,正当化論拠である。しかしまた,そのような社会的・必然的な単純商品流通はその背後に生産を想定せざるを得ない。単純な商品流通が想定するのは,私的な自己労働に基づいて生産物を私的に取得する個人的な私的生産者たちの社会,一言で言うと商品生産者たちの社会である。私的な商品生産者たちは,単に本源的に(生産過程での直接的な取得の結果として)自己の生産物を私的な自己労働に基づいて私的に取得しているだけではない。彼らが二次的に(商品の交換を通じて)他人の生産物を取得する時にも,それはただ等価物の譲渡によってのみ,すなわちただ自己労働に基づいて私的に取得している自己の生産物の譲渡によってのみ行われる。先ず,以上のような事実に基づいて,個別的な交換過程で個別的に,商品所持者たちは私的所有者として相互的に承認し合う。次に,ただこのような個別的な相互的承認の社会的な連鎖の中でのみ,彼らは私的所有者として社会的に承認されているのである。商品生産者たちの社会では,個別的な商品所持者たちの方が承認し合うのであり,これに対して社会の方はこの事実を追認するのに過ぎない。私法においては,個別的な私的行為が法律行為として妥当するわけである。このような仕方で毎日まいにち発生している所有が個人的な私的所有,一言で言うと私的所有なのである。このように,商品生産者たちの社会としての現代社会の基礎は私的労働(私的な自己労働)であり,またそれに基づく私的所有(個人的な私的所有)である。このような側面で,現代社会は商品生産が行われている社会,市場社会,自由主義社会である(その政治的な表現が民主主義社会である)。
しかしまた,現代社会は資本主義的な商品生産が行われている社会でもある。資本主義的な商品生産は商品生産の最も発展した形態であり,商品生産の必然的な帰結であり,単純な商品流通の諸法則に完全に準拠して発生する。それにも拘わらず,資本主義的な商品生産は先ず私的労働を止揚し,それに基づいて私的所有を止揚する。この両者を通じて,資本主義的な商品生産は私的生産を止揚する。資本主義的な商品生産は社会的な生産──始めには個別的資本の内部での社会的生産,やがては個別的資本の間での社会的生産──を展開する。一言で言うと,資本主義的な商品生産は商品生産を止揚する。逆に言うと,商品生産は,自己の最も発展した最も純粋な形態において,自己を徹底的に否定する。
しかしまた,資本主義的な商品生産は単なる社会的生産ではなく,敵対的・階級的な社会的生産である。それが社会的になるのは商品生産だからではあるが,しかし敵対的・階級的だからである(諸個人をバラバラな賃金奴隷として雇用し,徹底的に搾取するからである)。資本主義的な商品生産においては,総ての諸人格は自由でもなく,平等でもなく,私的所有者でもなくなる。資本主義的な商品生産において初めて自由・平等・私的所有は開花するが,しかし開花した時には既に散ってしまっているのである。
私的労働こそが──しかも個別的資本の直接的生産過程の内部での私的労働の止揚こそが──私的生産の止揚の出発点である。但し,資本主義的生産では,私的労働の止揚は物象的形態において──他人の労働として──成就される。いや,それどころか,私的労働の止揚はそれ自体として物象化の進展そのものである。これに対して,私的所有の止揚は,優れて物象の人格化において,私的労働の止揚を暴露し,必然的にし,制度的に固定化する。
株式会社は正にこの私的生産の止揚の延長線上にあり,その最高の形態であり,そのことによって資本の通過点的性格を暴露している。だから,株式会社論は私的所有の止揚に先行して,私的労働の止揚によって基礎付けられなければならない。これに基づかない株式会社論は私的所有の止揚の理論としても無意味である。但し,株式会社形態を株式会社形態にする形態的な本質は,正に私的労働の止揚が当事者意識に対しても暴露されているという点にあり,それ故にまた私的所有の止揚にある。
奥村に決定的に欠如しているのは,私的労働の止揚から出発するという点である。彼は正当にも私的所有の止揚──但し法人所有というその特殊的な一形態──に着目するが,そこから私的労働の止揚に遡ろうとはしていない。だからこそ,──奥村は自己の主張を徹底していないとは言っても,結局のところ,もし彼がそれを徹底するならば (注15) ──,彼の場合には,法人所有という所有形態の単なる解体が,それだけで,バラ色の未来を齎すはずなのである (注16) 。奥村の主観的な意図には関わりなく,客観的には,奥村は,“生産関係の基礎は所有関係であるから,もし所有形態が単に変革されさえすれば,バラ色の未来が齎される”と主張する最も見苦しいスターリン主義者(あるいは──これは左翼的スターリン主義者の右翼的別名であるが──新自由主義者)そのものである (注17) 。
B.商品の流通過程か,それとも資本の生産過程か
株式会社は資本の生産過程に基づいている。奥村の枠組みに即して言うと,生産過程の大規模化こそが既に株式会社を要請しているのであり,既に事実的・偶然的に経営者支配 (注18) を措定している。
株式会社は生産過程の社会的性格の暴露形態であり,real capitalにおいてもfiktives Kapitalにおいても自由・平等・私的所有という単純な商品流通の諸表象を否定している。株式会社においては,自由・平等な私的所有者の権利は徹底的に制限されている。ドイツ・日本の商法においては,自由・平等な私的所有者たちはそもそも株式会社の機関でさえない。彼らは社団の社員でありながら,会社の機関でさえない偶然的な人格に貶められている。定款で株式が譲渡制限されていない限りでは──そしてこれこそは大規模公開株式会社の理念である──,株主はヤクザであってもいいし,反原発市民運動ゴロであってもいいし,(日本ではまた)法人であってもいい。
但し,株式会社は,単純な商品流通の諸表象に徹底的に基づいて,単純な商品流通の諸表象を否定しているのである。株式会社は自由・平等な私的所有者たちが構成する社団でありながら,自由・平等な私的所有者はこの社団の内容から自己自身で自己を排除している。だから,株式会社は自由・平等な私的所有者の自己疎外である。単純な商品流通の諸法則の否定は,ただ単純な商品流通の諸法則の貫徹としてのみ現実的である(逆に,単純な商品流通の諸法則の貫徹は,ただ単純な商品流通の諸法則の否定としてのみ現実的である)。もしそれの否定とともに「最初の処女性〔virginité primitive〕」(Le Capital, p.509)も消え去ってしまうならば,既に共産主義が実現されているであろう!
実に正当なことに,奥村は,単純な商品流通の諸表象のコロラリである株主主権説などとは全く異なる資本の生産過程の実在性が当事者意識に対して暴露されているということを強調する。奥村が全く展開し得ないのは,このような実在性が暴露されているのにも拘わらず,何故に株主主権説がなくなりはしないのかということである。もし仮に“虚構”が単なる“嘘”であるのに過ぎないのであれば──もし仮にバカな一般ピープルが,ズル賢くワル賢い悪徳経営者(とその手先)によって騙されているのに過ぎないのであれば──,さすがにもうそろそろこんな素朴な嘘は消え去ってもいいはずだ。ところが実際には,奥村自身がいみじくも述べているように,「こんな虚構が堂々とまかり通っているのはまことに不思議な話である」(第16頁)のにも拘わらず,毎日まいにち虚構が生み出されているのだ。これこそは,客観的な関係そのものに基づかない偶然的な“嘘”と,客観的な関係そのものに基づく必然的な“虚構”とを区別するのだ。奥村に即して言うと,「現実離れした虚構」(第2頁)について,彼は,“それが何故に,どのようにして「現実離れ」せずにはいられないのか”ということを研究してはいるが,しかし,これに対して,“それにも拘わらず,それでもなお,何故に「虚構」が生じずにはいられないのか”ということを研究しようとはしない。奥村が行っているのは,せいぜい,虚構を笑い飛ばすだけのことである。貨幣について,“それはシンボルだ”と笑い飛ばすということによって貨幣の謎が消えてしまったと考えたフランス啓蒙思想家たちと同様に,結局のところ,奥村の態度は啓蒙的な態度に留まらざるを得ない。だから,奥村の主観的な意図に関わりなく,奥村の理論の徹底はこうなるべきである。──“バカな一般ピープル諸君,君たちは闇の謀略勢力に騙されているのだ。俺様は頭がいいから悪徳経営者の嘘を見抜いた。その俺様が君たち糞尿まみれの愚民どもを啓蒙してやるのだ”というわけだ!
(注19)
C.real capitalか,それともmonied capitalあるいは擬制資本か
株式会社において,real capitalはreal capitalとしての自己と擬制資本としての自己とに,始めには二重化し,やがては分裂していく。そもそも擬制資本運動とreal capital運動とは無関係である。大規模公開株式会社においては,擬制資本運動はreal capitalが与かり知らない運動であり,それが問題になるのはせいぜい敵対的買収の時くらいのものである。そして,擬制資本はreal capitalから,始めには額面価格として質的に,やがては時価として(流通市場で,いやそれだけではなく発行市場でさえ)量的にも分裂していく。real capitalとしての大規模公開株式会社にとっては,自由・平等な私的所有者は偶然的な人格であり,正当化のために必要な必要悪である。言うまでもなく,擬制資本発行はreal capitalとしての株式会社が自己の量的制限を突破するために必要なものとして要請したのであった。株式会社においては,real capital自身が擬制資本を要請しているのであって,その逆ではない。
しかしまた,擬制資本発行によって,自己の量的制限を突破してしまうや否や,今度はこの制限突破の形態自体が自己にとっての制限になっている。いまでは,自己を正当化するためには,株式会社は否が応でも株式を株券という形態で発行せざるを得ない。
商法が想定している大規模公開株式会社では,自由・平等な私的所有たちは,fiktives Kapitalの所有に基づいてケチな配当を受け取る金利生活者であろうと,それとも神聖な私的所有権の証書をあろうことか投機の道具にし,従ってまた次から次へと自己の私的所有を株券売買によって否定していく一発屋であろうと,いずれにせよ自己の金儲けの根拠である直接的生産過程から徹底的に疎外されている。私的所有者にとって会社は自己から疎遠な──自己に敵対的な──金儲けの道具であり,逆に,会社にとって私的所有者はコスト(=株主コスト)である。客観的には,私的所有者にとって会社は,私の出資のおかげで成り立っているのにも拘わらずあろうことか非情にもその経営から私を徹底的に排除している恩知らずのガキであり,逆に,会社にとって私的所有者は,会社経営に汗水流していないのにも拘わらずあろうことか強欲にも儲けの分け前(=配当)を請求したり,会社が赤字になっても倒産しても責任をとらないのにも拘わらずあろうことか卑劣にも会社の成果を有価証券売却益という形で横取りしたりする薄汚いブタである。私的所有者が成しうるのはせいぜいチェックである。私的所有者は所有者から債権者に成り下がっている。私的所有者の権利は物件的権利(絶対的権利)から債券的権利(相対的権利)に貶められている。ところが,正に私的所有権が物件的権利であるということにのみ,株式会社の正当性は依存しているのである。社債しか発行せず,株式を発行しないような株式会社は薄汚い従業員たちが物象的に構成する専制団体,従業員たちの共同不法占拠(Gemeinbesitz!)であって,しかるに自由・平等な私的所有者たちが人格的に構成する (注20) 民主的な株式会社ではない。会社にとって(もちろん株主にとっても)株式は社債と同様な意味しかもっていないのにも拘わらず,会社は株式を止揚し得ない。委任状についても,事柄は全く同様である。株主総会が成立しない株式会社は不法な株式会社である。real capitalとしての株式会社にとっては,株主は株主総会に出席してはならず──と言うのも,株主は自由な資本運動を監視するチェック野郎だから──,しかも出席しなければならない──と言うのも,正にこのような制限こそが資本の物象的運動の人格的実現の場面であるから──。この矛盾を──止揚するわけではないが──媒介するのが委任状である。
このように,資本は自己の限界(Grenze)を制限(Schranke)として乗り越えるのであるが,正に制限を乗り越えてしまうということによってこそ,自己の限界を暴露してしまうのである。──“昨日までの私を私は窮屈に感じていた。私は今日からの私に生まれ変わった。だが,昨日までの私も今日からの私も同じ他ならぬ私なのだ。私は私自身を窮屈に感じているのだ”。制限突破の形態は新たな制限であり,しかも自己解体的な制限である。限界を(乗り越えられるべき窮屈な制限として感じるのではなく)快く感じるようになれば,永遠の停滞の中で,資本主義社会は永遠に存続してしまうかもしれない!
D.物象の人格化か人格の物象化か
既に強調したように,real capitalこそが擬制資本運動を措定するのであって,その逆ではない。これこそは発生史論的な株式会社論(典型的には大塚久雄,しかし一般的には殆ど総てのマルクス経済学者たち)と理論的な株式会社論とを区別する決定的な分水嶺である。しかしまた,real capitalの運動から株式会社を把握する時にも,どうやら二つの道があり得るようであり,これがまたもや分水嶺になるであろう。第一の道は物象化から人格化を導出する道であり,第二の道は人格化から物象化を導出する道である(図6)。すなわち,第一の道では資本という物象的な運動主体の自己運動が株主総会という制度的・人格的な妥当形態を措定し,第二の道では株主総会という制度的・人格的な妥当形態が資本の運動を措定する。もう少し解りやすく言うと,第一の道は経営者支配現象から株主総会形骸化を説明し,第二の道は株主総会形骸化から経営者支配現象を説明する。われわれの道は第一の道であり,どうやら奥村の道は第二の道であるように思われる。
既に見たように,第一に,奥村は株式会社論を株式論(fiktives Kapital)としてではなく,会社論(real capital)として展開しようとしているようである。その限りでは,奥村の株式会社論はreal capitalから出発している。しかしまた,──これは必ずしも一貫しているわけではないが──,奥村にとってreal capitalは,何よりもまず,諸人格の物象化ではなく,物象の人格化の場──株主総会──であるようである。
第二に,奥村は経営者支配現象をreal capitalとしての株式会社が生まれつきもっている本質としてではなく,株式会社によって──しかも株式の,つまり擬制資本の大量発行を通じて──ようやく措定される形態として把握している。ここでも,奥村は経営者支配現象の究極的な原因をを株式会社の大規模化に──その限りではreal capitalとしての株式会社の本質に──求めている。しかしまた,単なる大規模化によっては経営者支配現象は発生し得ないというのが,奥村の(あるいは通常の社会諸科学の)経営者支配現象論のポイントなのである。奥村にとっては,経営者支配現象は会社(real capital)の大規模化が株式(fiktives Kapital)の大量発行に至った時に初めて発生する。言うまでもなく,このような把握態度は過去の歴史的形態の把握態度としては正しい一面を──しかしまた単なる一面を──含んでいる。ところが,奥村が問題にしているのは,正に,過去の歴史的な株式会社ではなく,現在の株式会社なのである。
企業:機能から資本を把握しようとする社会通念。firm, enterprise, corporation。従業員組織。
会社:所有から資本を把握しようとする社会通念。company。社員組織。
II.個別的問題
1.機関化現象と法人化現象
機関化現象と法人化現象との区別は理論のどのレベルで現れるべきものであるのか。
奥村は日本資本主義の特殊性を主張するために,株式の相互持合いに着眼した。この着眼点からは,アメリカでの機関化現象と日本での法人化現象との区別は決定的であった。だからこそ,奥村は資本主義社会における信託一般の形骸化をどうしても忘れようとする。
アメリカで機関投資家という場合,具体的には年金基金,投資信託,生命保険などをさしているが,これらはいずれも受益者である個人に代わってその資産を株式や債券などで運用しているのであり,銀行や事業会社が自己の資産として株式を所有している法人所有とは異なる。〔第57頁〕
と言うのも,もし信託一般が形骸化してしまうならば──いやそもそももしエージェントが必然的にプリンシパルから自立化してしまうならば──,アメリカ資本主義と日本資本主義との間での区別は決定的ではなくなるからである。もしそうならば,アメリカでの機関化現象も日本での法人化現象も同じ原因に基づくものであり,それ故にまた両者の差異は相対的なものになってしまうであろう。
しかし,両者の差異が相対的であるということは疑いようがない事実であるから,恐るべき二枚舌で,次のように述べるのである。
いわんや機関投資家によって株主総会が活性化するという見通しはない。というのも機関投資家のファンド・マネジャーは他人の資産を運用している代理人でしかなく,その地位は不安定である。そして受益者である年金受給者や投資信託の加入者がどこまで会社支配に関心を持っているか,そしてそれがファンド・マネジャーを動かすことができるのかどうか,疑問だからである。〔第61頁〕
もしそうであるならば,機関化現象も法人化現象も全く同じ意義を持っていると言うべきである。そしてこれはそもそも株式会社の本質──いやそれどころか資本主義の本質──に根差しているのである。
奥村にとっては株式の持ち合い現象は決定的である。(何故ならば,既に見たように,奥村にとっては日本的資本主義とアメリカ的資本主義との制度的な区別こそが最も決定的であり,しかるにアメリカには株式持合いは制度的に実存しないからである)。だからこそ,彼は今度は,株式の“法人所有”と“機関所有”とを区別し,前者を日本的システムの特徴にしようとする。
参照文献
-
引用和文中の傍点での強調は著者自身,下線での強調は今井による。
-
文中での引用と参照指示とで書名・論文名が省略されてページ数だけが書かれている場合には,それは『株主総会』からの引用である。また,その場合には,ページ数の“第[n]頁”は『株主総会』のページを指示している。
- AW
- Karl Marx / Friedrich Engels Ausgewählte Werke, Dietz Verlag, Berlin.
- MEGA2
- Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe, Dietz Verlag, Berlin.
- Manifest
- Manifest der Kommunistischen Partei, In: AW, Bd.1.
- Kr
- Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft, In: MEGA2, II/2.
- Le Capital
- Le Capital. Paris 1872--1875, In: MEGA2, II/7.
- 奥村宏(1984)
- 『法人資本主義──「会社本位」の体系』,お茶の水書房〔『[改訂版]法人資本主義──会社本位の体系』,朝日新聞社,1991年,から引用〕
- 奥村宏(1976)
- 『日本の六大企業集団』,ダイヤモンド社〔『日本の六大企業集団』,朝日新聞社,1994年,から引用〕
- 奥村宏(1991)
- 『証券スキャンダル』,岩波書店
- 平子友長(1991)
- 『社会主義と現代世界』,青木書店
注
-
(注1) このことは必ずしも明確ではない。実際にまた,例えば彼の主著である奥村(1984)でも,第2章で「日本的株式会社」が,また第3章で「経営者」が扱われている。しかしまた,奥村はこうも言っている。──「これまで法人資本主義論を二〇年以上にわたって主張してきた私としては,かねてから株式会社論を本格的に展開していきたいと念願していた」(第217頁)。と言うことは,奥村は,彼自身の主観においては,これまでは株式会社論をただ法人資本主義のシステム論に必要である限りで触れてきたのに過ぎず,しかるにそれ自体として「本格的に」は取り扱ってこなかったということであろう。
-
(注2) 「このような株主総会とはいったい何なのか。これは株式会社のあり方の根本にかかわる問題である。ということは株主総会を解剖することは株式会社そのものを解明することにつながる」(第217頁)。「そこで本書では株主総会に焦点をあてることによって株式会社を解剖しようとした」(第218頁)。
-
(注3) 「そこには日本の株主総会の特異なあり方があるのだが,総会屋スキャンダルで最も重要な問題はこの日本の株主総会のあり方である。〔……〕問われているのは総会屋を成り立たせている日本の株主総会そのものである」(第6頁)。すなわち,奥村が問題にするのは個別的な株主総会ではなく,「株主総会そのもの」──株主総会の一般性──であるが,但し「日本の株主総会そのもの」──株主総会一般の日本的な特殊性──なのである。
-
(注4) 通常,商法の教科書では,自己株式取得の弊害としては,自己資本充実原則に反するということの他に,一部の株主からの株式買付けによって株主間での売却機がの不平等になるということ,乗っ取り防止のための自己株式取得によって経営者支配が固定化されるということ,インサイダー取引などによって投機が助長されるということなどが挙げられている。
-
(注5) 「しかし同時に株主代表訴訟には原理的に見て大きな制約があることを忘れてはならない。なによりもこれは株主の立場に立った訴訟であり,そして取締役に会社に対して損害の賠償をせよというものである。ということはこれは会社は株主のものであるという前提に立って,会社のために経営者に損害賠償を求めるということである。いわば株主=会社が取締役を訴えているのである。ところが日本では取締役は会社と一体化しており,取締役=会社となっている。そこで取締役が会社のために政治献金をしたり,汚職をしているのが普通であり,それは会社のためにやった行為だから,株主が会社の立場に立ってそれを批判することはできない」(第47〜48頁)。
なお,奥村はこの事態が絶対的・永久的であると考えているようである。しかし,当事者意識上での株主についての表象の変化によって,そのような事態はいくらでも変化し得るのである。そもそも株主代表訴訟それ自体が,会社法の破綻──会社法の理念とは異なる経営者支配現象の露出──を前提にしているのである。とは言っても,もちろん,株主についての表象の変化の司法的な表現がどの実定法を利用するのかということは,偶然的である。
-
(注6) 「株式会社の規模が大きくなると資本金が増え,株主の数も増える。最初は資本家,すなわちオーナー株主が過半数の株式を所有し,それによって会社を支配していたがやがて多くの株主が株式を所有するようになると,資本家株主は過半数以下の株式でも会社を支配できるようになる」(第50頁)。言うまでもなく,奥村の場合には,このような発生的な序列は歴史的な序列であるだけではなく,理論的な序列でもある。とは言っても,奥村は両者を区別してはいないのであるが。ここで,われわれは,奥村の議論では,第一にreal capitalが出発点であるということ,しかし第二にreal capitalによっては経営者支配が生まれ得ない──株式発行の長期的な結果として初めて経営者支配が生まれる──ということを確認しておこう。結局のところ,奥村には資本の直接的生産過程の理論が根本的に欠如しているのである。言うまでもなく,これは直接的にはバーリ及びミーンズの欠点であり,間接的には殆ど総ての“マルクス主義的”株式会社論者の欠点である。なお,この点についての考察は,奥村に対する内在的批判を大きく踏み越えるものであるから,問題点のところで詳論したい。
-
(注7) 「これら〔=年金基金,投資信託,生命保険などの機関投資家〕はいずれも受益者である個人に代わってその資産を株式や債券などで運用しているのであり,銀行や事業会社が自己の資産として株式を所有している法人所有とは異なる」(第57頁)。
-
(注8) 以上について,奥村は第3章でより詳しく論じている。
-
(注9) 奥村は,企業集団は,放射状の類型では成立せず,ただ円環状の類型でのみ成立すると考えているようである。──「いわゆる独立巨大企業における相互持ち合いが放射状であるのに対して企業集団における場合は円環状,マトリックス型になっているのである」(奥村(1976),第140頁)。
-
(注10) 「いったんこのような相互信認の論理が財界の中で確立すると,株式相互持合いの相手とだけではなく,一方的所有の関係にも援用される」(第69頁)。「それならば生命保険会社は大株主として株主総会で会社側に圧力を加えるべきではないか。しかし生命保険会社が株主総会でそういう行動に出たという話は聞かない。ここがアメリカの機関投資家と異なるところだが,このことは日本では機関投資家にも法人と同じような相互信認の論理が浸透しているということである」(第70〜71頁)。
-
(注11) 「「誰が会社を支配しているのか」を議論する場合には,誰が会社の重要な方針を決めているのか,ということが問題になる。そこで普通は経営者が会社の重要な方針や政策を決定しているので,その経営者を誰が決めているのかということが問題になる。株式会社についてみると,大株主である資本家が経営者を決めているのなら所有者支配ということになるし,経営者が経営者を決めているのなら経営者支配ということになる。もし従業員が経営者を決めているのなら従業員支配ということになるし,政府が決めているのなら国家支配,あるいは官僚支配ということにもなる」(第76頁)。
-
(注12) 「というのは日本の大企業の取締役や監査役のほとんどは従業員出身であり,なかには労働組合の執行委員をしていた人が取締役になったり,社長,あるいは頭取になったというケースも多いからだ。これをもって日本の大企業では従業員支配になっているという人もいるが,しかし従業員出身ということと,従業員代表ということとは違う。従業員から経営者になったという人はアメリカやヨーロッパにも多いが,誰もそれをもって従業員支配とは言わない。それは豊臣秀吉が百姓出身だからといって,豊臣政権を百姓支配と言わないのと同じだ」(第77〜78頁)。
-
(注13) この議論がやや解りにくいのは,支配とチェックとを混同しているからである。社会意識相関的に──支配の諸類型の問題として──問題を立てるとしても,奥村は,(1)そもそも株式会社では始めから経営者が支配しているのであり,その他の諸機関,諸個人は総て悉くチェック機能しか演じ得ないということを大前提にして,(2)その上で果たして本当に日本ではそのようなチェック機能が機能しているのかと問題を立てるべきであった。
-
(注14) 以上の点に関する奥村の説明はやや解りにくい。そこで,私は自分自身の理解に基づいて奥村の説明を整理した。奥村の説明が解りにくいのは,既に述べたように,自由な私的人格による会社“支配”のことを論じようとしながら,事実上,不自由な会社機関(取締役および取締役会)のチェック機能のことを論じてしまっているからである。
転回は株式会社の中で生じているのと同様に,奥村の脳髄の中でも生じているのである。 -
(注15) 自己の主張を徹底しないということは理論家にとっては
破廉恥な批判されるべきであるが,健全な常識をもつ思想家にとっては賞賛されるべきことである。何故ならば,資本主義社会それ自体が二枚舌であり,二重人格である(つまり全く相反する二面的な意識を産み出す)からである。つまり,なんらかの超越的な理論的公準にしがみつくのではなく,事実そのものにしがみつく限りでは,主張は徹底され得ないわけである。そして,奥村は,思想家と言うよりは寧ろジャーナリストであるが,しかしいずれにせよ,疑いなく,理論家ではない。もちろん,われわれがここで批判しているのは,奥村の理論であって,しかるに奥村の人格では決してない。 -
(注16) 第一に,奥村の短期的な政策目標として解釈され得る株主総会活性化については,なるほど彼は「株主総会を活性化するためには,会社のあり方そのものを変えていく以外にはない」(第176頁)と主張してはいる。しかし,われわれが「会社のあり方そのもの」の変革(突き詰めて言うと,生産関係そのものの変革)として奥村の主張の中に実際に見出し得るのは,結局のところ,ただ株式の法人所有の禁止(所有関係の変革)だけである。──「株主総会を活性化するには法人株主にメスを入れる以外にはない」(第181頁)。奥村は理論的に一貫していないから,これは非常
非情に微妙なところであるが,われわれは,“結局のところ,奥村が言う「会社のあり方そのもの」の変革とは,法人の株式所有の禁止のことである”と判断せざるを得ない。第二に,奥村の長期的な政策目標として解釈され得る大規模株式会社の解体については,奥村は更に一層,動揺している。しかし,ここでもやはり,もし奥村が自己の主張を一貫させるならば,大規模株式会社の解体もまた所有形態の変革とイコールであると,われわれは判断せざるを得ない。先ず,既存の大規模株式会社そのものの解体については,微妙な表現ではあるが,「日本の会社の分社化,別社化が本当に分権化を目的にしているのなら,これを完全に独立の会社にし,親会社による株式所有をやめるべきである」(第207頁)と,奥村は主張している。次に,既存の大規模株式会社にとって代わるべき新しい小規模企業の生成については,奥村は「様々なタイプの新しい企業」として合名会社,協同組合,郷鎮企業などを列挙している。しかし,それらの区別も,奥村の主張の中で理論的に正当に位置付けられ得る限りでは,すなわち単なる規模の大小を越えるものであるなら
れば──そして単に規模が小さいのに過ぎない小企業は「新しい企業」では決してなく,そうではなく,われわれが今でも既に日常的に目にしており,しかも今日の大企業体制を底辺で支えている“古くさい”タコ社長企業である──,やはり所有形態の単なる相違であると,われわれは判断せざるを得ない。言うまでもなく,私的所有の止揚の問題──従ってまた所有形態の自覚的な変革の問題──は,正に社会意識相関的であるからこそ,常に運動の出発点であり続け,常に運動のスローガンであり続ける。生産関係の変革は,常に必ず,所有関係の変革によって自覚化されなければならない。──「これら総ての運動において,共産主義者は所有の問題を──それがとっている形態が発展していようといまいとも──運動の根本問題として強調する(Manifest, S.451)。「この意味で,共産主義者は自己の特徴を,私的所有の止揚という一言で纏めて表現し得る」(a.a.O.,S.430)。しかしながら,それは実在的労働過程そのものと現実的生産関係そのもののとの資本主義の枠内での変革の社会意識相関的な表現であり,それ故にまた実在的労働過程と現実的生産関係との根本的な変革のために必要な宣言だからである。
-
(注17) 生産関係の基礎が所有関係にあるという見解は優れてスターリン主義を特徴づけるものであるが,しかし,左翼(マルクス主義)の内部ではスターリン主義であろうと反スターリン主義であろうとも,また社会常識の内部では左翼であろうと右翼であろうとも,非常に広く通用している。つまり,一方では,私有企業を国有化すれば新しい社会が生まれるという観念があり,他方では,国有企業を私有化すれば新しい社会が生まれるという観念がある。また,両極の間には,国有化と私有化とをどのように配分すれば新しい社会に移行し得るのかということに応じて,無限に多様な観念があり得る。これらの観念の総ては,所有関係の変革と新しい社会の到来とを等置するという点で共通している。
マルクス主義の内部について言うと,このような見解があまりにも立場を問わずに広く通用しているから,平子友長は,それがマルクス自身の見解だと真面目に信じ込んでいるほどである(平子(1991),第76頁)。しかも,あろうことか,平子はその文献的根拠を『経済学批判』の序文に求めているのだ! ところが実際には,マルクスはそこではハッキリと「現存する生産諸関係に,あるいは──これは生産諸関係にとっての法制度的な表現であるのに過ぎないのだが──所有諸関係に〔mit den vorhandenen Produktionsverhälnissen, oder was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigenthumsvrhältnissen〕」(Kr, S.100)と明言しているのだ! 人間の嘔吐物の「表現」をゲロに変えようとヘドに変えようとも,それが汚いものであるということには変わりがないではないか! 『経済学批判』の序文には様々な叙述上の問題があるが,それにしても,いくらなんでも,たとえどのような叙述上の制約があろうとも,マルクスがあれほど精力的に批判したプルードンの法学幻想の立場を受容するかのような叙述を,マルクス自身が行うわけがないのだ! 総てこのような試みは笑い話に帰着するが,しかし平子のような真面目なマルクス研究者さえも,マルクスのテキストによってではなくスターリンによってマルクス像を形成しているということは笑い話にはならない。
-
(注18) われわれの立場から見ると,「支配」しているのは経営者ではなく,資本そのものである。ここでわれわれが「経営者支配現象」という名辞を用いるのは,単にそれが大いに普及しているからであるのに過ぎない。議論に前提される表象は,大規模公開株式会社としてイメージされるものにおいては,エージェントがプリンシパルから自立化しているということ,しかしまたそれにも拘わらず,プリンシパルがエージェントにとっての制約になっているということ──これだけである(要するに,会社は株主のものでありながら,実際には株主のものにはなっていないという,現代人は誰でも抱いている表象だけである)。それ以外の特殊的な表象(或る会社では悪徳資本家がいるとか,或る会社では経営者と資本家とが一致しているなどという表象)は,公共的な議論にとって妨げにしかならない。
-
(注19) 言うまでもなく,これは彼の理論的態度の徹底の必然的・客観的な帰結であって,偶然的な個人である彼自身の主観においては,このような帰結は,もちろん,拒絶するべきものであろう。しかし,このことは,それはそれで,彼自身が自己の理論的態度を徹底していないということを証明しているのに過ぎない。なお,この報告の注15をも参照せよ。
-
(注20) 株式会社は人的会社ではなく物的会社として表象されているが,それでもやはり財団法人ではなく社団法人として表象されているのである。会社財産が基礎になっているとは言っても,他ならない会社財産を成り立たせているのは,社員関係に置き換えられた人格的な相互的関係である。